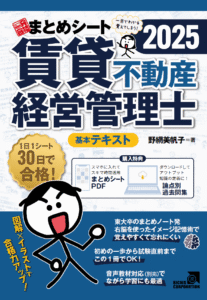今日は、平成28年度 第34問について解説します。
不動産証券化とプロパティマネジメントに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 平成10年に特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(現在の「資産の流動化に関する法律」)が制定され、SPCが証券を発行して投資家から不動産への投資資金を集め、不動産を購入して賃料収入を取得し、賃料収入を投資家に配分できるようになった。
② 平成19年3月改正の不動産鑑定評価基準では、DCF法の適用過程の明確化の中で、収益費用項目の統一化が図られ、PMフィーは運営収益として計上されるようになった。
③ プロパティマネジメント会社は、アセットマネージャーから委託を受け、その指示の下にプロパティマネジメント業務を行う。
④ アセットマネジメントは、実際の賃貸管理・運営を行うのに対し、プロパティマネジメントは、資金運用の計画・実施を行う。
解説
不動産証券化とプロパティマネジメントに関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
平成10年に特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(現在の「資産の流動化に関する法律」)が制定され、SPCが証券を発行して投資家から不動産への投資資金を集め、不動産を購入して賃料収入を取得し、賃料収入を投資家に配分できるようになった。
×不適切です
1998年(平成10年)に制定された「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(資産流動化法)」に基づき、特定目的会社(TMK)が証券を発行し、投資家から不動産への投資資金を集め、不動産を購入して賃料収入を取得し、賃料収入を投資家に配当することができるようになりました。
つまり、平成10年に特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(現在の「資産の流動化に関する法律」)が制定され、TMKが証券を発行して投資家から不動産への投資資金を集め、不動産を購入して賃料収入を取得し、賃料収入を投資家に配当できるようになりました。よってこの選択肢は不適切です。
なお、SPC(特別目的会社)は広範な資産の証券化を行うことができる器の総称です。
そのうち、資産流動化法に基づいて設立された法人は、特定目的会社(TMK)といい、TMKはSPCの1つの形態にあたります。
選択肢 ②
平成19年3月改正の不動産鑑定評価基準では、DCF法の適用過程の明確化の中で、収益費用項目の統一化が図られ、PMフィーは運営収益として計上されるようになった。
×不適切です
平成19年に一部改正された不動産鑑定評価基準では、証券化対象不動産の鑑定評価に関する基準が設けられました。
ディスカウント・キャッシュフロー法(DCF法)は、不動産の収益価格を求める手法の一つですが、この改正により証券化対象不動産の収益価格算定に当たってはDCF法を適用することとされました。
また、それまで不動産鑑定士によって扱いにばらつきがあった収益費用項目について、統一的な区分と定義の明確化が行われました。その中で、PMフィー(プロパティマネジメント費用)は運営費用として計上されることが明確化されました。
つまり、平成19年3月改正の不動産鑑定評価基準では、DCF法の適用過程の明確化の中で、収益費用項目の統一化が図られ、PMフィーは運営費用として計上されるようになりました。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
プロパティマネジメント会社は、アセットマネージャーから委託を受け、その指示の下にプロパティマネジメント業務を行う。
〇適切です。
プロパティマネジメント(PM)は、実際の賃貸管理・運営を行うことをいいます。
アセットマネージャーから委託を受け、その指示に基づいて業務を行うのがプロパティマネジメント会社(プロパティマネージャー)です。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
アセットマネジメントは、実際の賃貸管理・運営を行うのに対し、プロパティマネジメントは、資金運用の計画・実施を行う。
×不適切です
アセットマネジメント(AM)は、投資家から委託を受けて、①総合的な運用計画の策定、②投資を決定・実施、③PM会社への業務委託、④PM会社から報告を受けて投資状況を把握し、⑤現実の管理・運営の指示、⑥売却による投下資金回収という一連の業務です。
また、プロパティマネジメント(PM)は、実際の賃貸管理・運営を行うことをいいます。
つまり、プロパティマネジメントは、実際の賃貸管理・運営を行うのに対し、アセットマネジメントは、資金運用の計画・実施を行います。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
【選択肢②について】
選択肢②は、不動産鑑定評価基準に関する知識も必要であり、「聞いたことない単語が出てきた…」と不安になる方もいるかもしれません。
令和7年度の公式テキストを確認しましたが、不動産鑑定評価基準やDCF法に関する記述は見られませんでした。
そのため、試験に出題される可能性は低いと考えられます。
ですので、もしこの選択肢がわからなかったとしても、この解説を読む程度で十分です。(深追い不要です)
一方で、選択肢③および④は必ず押さえておきたい内容ですので、もし③、④で迷った方は、テキストでしっかり復習しておくことをおすすめします。
ぜひ関連解説もあわせてご確認いただければと思います。
★関連解説★
プロパティマネジメントとアセットマネジメント(R2年 第45問)
プロパティマネジメントとアセットマネジメント(R4年 第50問)