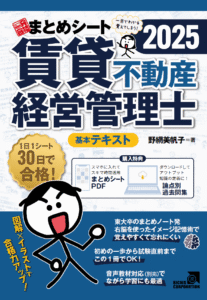今日は、平成27年度 第10問について解説します。
A所有のマンションの一室を、管理業者であるBがAから賃借し、Cに転貸している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
① AB間の月額賃料が20万円、BC間の月額賃料が18万円の場合、CはAに対して20万円の支払義務を負う。
② AB間の賃貸借契約が終了し、それがCに対抗できる場合には、CはAに対して賃貸物件の返還義務を負う。
③ AがAB間の賃貸借契約の更新を拒絶する場合には、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではないCの事情は考慮されない。
④ AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は終了しない。
解説
転貸借に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
AB間の月額賃料が20万円、BC間の月額賃料が18万円の場合、CはAに対して20万円の支払義務を負う。
×不適切です
貸主(所有者)が転貸借を承諾していて、転貸関係が有効に成立している場合には、貸主は転借人(入居者)に対しても直接、賃料の支払いを求めることができます。
ただし、請求できる賃料の額には上限があり、貸主が転借人に対して請求できるのは、転貸人の債務の範囲に限られており、具体的には、原賃貸借契約における賃料と、転貸借契約における転借料のいずれか低い方の金額までとなります。
つまり、AB間の月額賃料が20万円、BC間の月額賃料が18万円の場合、CはAに対して18万円の支払義務を負います。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
AB間の賃貸借契約が終了し、それがCに対抗できる場合には、CはAに対して賃貸物件の返還義務を負う。
〇適切です。
転貸借が行われているときに原賃貸借契約が終了した場合、その終了の原因などによって、転貸借契約への影響や内容が異なります。
選択肢の場合は、終了原因は明記されていませんが、「AB間の賃貸借契約の終了がCに対抗できる」ため、原賃貸人(A)は転借人(C)に対して建物の明渡しを請求することができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
AがAB間の賃貸借契約の更新を拒絶する場合には、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではないCの事情は考慮されない。
×不適切です
契約期間の満了によって建物賃貸借契約を終了させるには、期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶等の通知をする必要があります。
この通知は、貸主・借主のどちらからでも行うことができますが、貸主が更新を拒絶する場合には、更新を拒否するのが正当と認められるだけの理由(正当事由)が必要です。
なお、建物が転貸されている場合には、転借人の事情も含めて更新拒絶の正当事由が判断されることになります。
つまり、AがAB間の賃貸借契約の更新を拒絶する場合には、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、転借人であるCの事情も考慮されます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は終了しない。
×不適切です
賃料の不払いなど転貸人(B)の債務不履行によって原賃貸借契約が解除され、契約が終了した場合には、原賃貸人(A)は転借人(C)に対して建物の明渡しを請求することができます。
この場合、BはCに対して使用・収益させるという契約上の債務を履行できない状態になるため、転貸借契約も履行不能によって終了します。
つまり、AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求した場合、Bの債務不履行によりBC間の転貸借契約も終了します。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。
★関連解説★
2025年度版 一発合格まとめシート おかげさまで好評販売中!