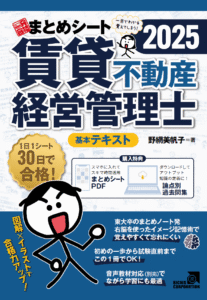今日は、平成27年度 第20問について解説します。
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約の再契約について貸主を代理して締結する場合には、宅地建物取引業法の定めるところにより、あらためて重要事項説明をしなければならない。
② 定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行えば足りる。
③ 平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別にかかわらず、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
④ 定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別個独立の書面で行わなくても足りる。
解説
定期建物賃貸借契約に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約の再契約について貸主を代理して締結する場合には、宅地建物取引業法の定めるところにより、あらためて重要事項説明をしなければならない。
〇適切です。
定期建物賃貸借契約における再契約時には、新たに契約を締結することになるため、宅建業者が代理・媒介して契約する場合には宅建業の免許が必要です。
この場合、宅建業者は宅建業法に基づき、契約締結前に宅建士が記名した書面を交付し、重要事項の説明をする必要があります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行えば足りる。
×不適切です
定期建物賃貸借を有効に成立させるためには、契約締結前に、契約の更新がなく期間の満了により終了することについて、あらかじめ借主に説明することが必要です。
この事前説明は、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明とは別に行う必要があります。
ただし、重要事項説明書に更新がない旨など必要な事項が記載されており、かつ、貸主から代理権を授与された宅地建物取引士が説明を行った場合には、事前説明書の交付および事前説明を兼ねることができるとされています。
つまり、定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行うだけでは足りません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ③
平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別にかかわらず、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
×不適切です
定期建物賃貸借制度は、借地借家法の改正により平成12年3月1日に導入されました。
これより以前に締結された居住用建物の普通建物賃貸借契約については、貸主と借主が合意により契約を終了させ、同一建物について新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていません。
一方で、事務所や店舗などの事業用建物については、この制限の対象外とされており、契約の締結時期にかかわらず、普通建物賃貸借契約から定期建物賃貸借契約への切替えが可能です。
つまり、平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用の場合、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別個独立の書面で行わなくても足りる。
×不適切です
定期建物賃貸借契約の事前説明は、契約書とは別の独立した書面で行う必要があります。
書面の交付や説明がなされていなかった場合には、定期建物賃貸借としての効力は認められず、普通建物賃貸借契約として扱われます。なお、この事前説明書は電磁的記録によって提供することも認められています。
つまり、定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書とは、別個独立の書面(または電磁的記録で提供)で行わなければ定期建物賃貸借契約としての効力は認められません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢①となります。
ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。
★関連解説★
2025年度版 一発合格まとめシート おかげさまで好評販売中!