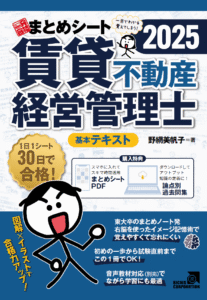今日は、平成28年度 第14問について解説します。
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付する、または電磁的方法で提供することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。
② 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。
③ 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
④ 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。
解説
定期建物賃貸借契約に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付する、または電磁的方法で提供することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。
×不適切です
定期建物賃貸借を有効に成立させるためには、契約締結前に、契約の更新がなく期間の満了により終了することについて、あらかじめ借主に説明することが必要です。
この事前説明は、契約書とは別の独立した書面で行う必要があり、書面の交付や説明がなされていなかった場合には、定期建物賃貸借としての効力は認められません。
つまり、定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付する、または電磁的方法で提供することとともに、口頭での説明が必要です。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。
〇適切です。
契約期間が1年以上である場合は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、貸主が借主に対して期間満了により終了する旨の通知を行わなければ、契約の終了を借主に対して主張することができません。
ただし、この期間内に終了通知が行われなかった場合でも、期間経過後に貸主が借主に対して終了通知を行えば、その通知日から6か月を経過した後に、契約の終了を借主に主張することができます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
×不適切です
定期建物賃貸借の場合、契約期間の下限は設けられていないため、1年未満の契約期間も有効とされています。
また、終了した従前の契約と再契約後の契約は別個のものであり、従前の契約期間は、再契約後の契約期間に影響を及ぼすものではありません。
つまり、契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することもできます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。
×不適切です
定期建物賃貸借契約の保証人は、契約が期間満了後に再契約された場合であっても、新たに保証契約を締結しない限り、再契約後の債務について保証債務を負いません。
つまり、定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合であっても、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負うことはありません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
※借地借家法の改正に伴い、選択肢①を改題しております。(「電磁的記録」の表現を加えるなどの一部改題を行っております。)
本試験での出題「選択肢①:定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。」
ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。
★関連解説★