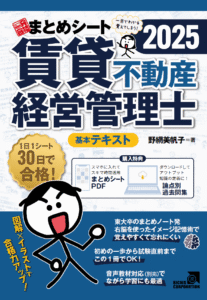今日は、平成28年度 第20問について解説します。
賃貸不動産の修繕に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができる。
② 借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができる。
③ 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。
④ 区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる。
解説
修繕義務に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができる。
〇適切です。
必要費は、建物を現状のまま適切に使用・維持するために必要な費用であり、本来は貸主が負担すべきものです。
そのため、借主が必要費を支出した場合には、貸主に対して直ちに償還を請求することができます。これを必要費償還請求権といいます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができる。
△注意が必要な選択肢です。
借主には修繕受忍義務があり、貸主が建物の保存のために必要な修繕を行おうとする場合、借主はこれを拒むことはできません。
したがって、借主が正当な理由なく修繕や保守点検の立ち入りに応じない場合、それが信頼関係を破壊する事情にあたると評価されれば、契約解除の理由となることがあります
つまり、借主が修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することが認められる場合もありますので、借主が修繕のための立ち入りを拒否する行為は、契約解除の事由となり得るという点では妥当といえます。
ただし、この選択肢のように「賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主が解除できる」と断定する表現は、民法607条の文言の一部を貸主側に読み替えたような構成になっており、やや違和感があります。
【民法607条】賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
このように、「目的を達することができない場合に解除できる」とされているのは借主の権利についてです。
その一方で、判例では、借主が保存に協力しないことで賃貸借契約の目的が果たせなくなった場合に貸主による解除を認めたケースもあります。
したがって、この選択肢は完全に不適切とはいえないものの、条文とのずれに注意すべき記述です。
選択肢 ③
貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。
×不適切です
貸主の修繕義務の対象となるのは、入居中に生じた損傷だけではなく、借主の入居前から存在する建物の欠陥や、地震などの不可抗力による損傷も含まれます。
つまり、貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られませんので、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負います。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる。
〇適切です。
貸主の修繕義務は、借主が使用する専有部分だけでなく、建物の共用部分も含まれます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
【補足】選択肢②について
近年は試験問題の精度も向上しており、こうした解釈に幅のある微妙な表現の選択肢はあまり出題されない傾向にあります。(そのかわり?問題文は長くなっている傾向がありますね。)
なお、公式テキスト(令和7年度版)には、次の内容が明記されています。
-
借主には修繕受忍義務があること
-
修繕受忍義務に違反した場合は契約解除の理由となり得ること
-
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合に、賃借人がその目的を達成できなくなるときは、賃借人は契約解除ができること(民法607条)
この3点を押さえておけば、試験対策としては十分対応可能でしょう。
また、本問は「最も不適切なものを選ぶ」という形式ですが、選択肢③は「入居前からの雨漏りに修繕義務がない」とする点が明確に誤りであり、正解として疑いのない肢です。
そのため、選択肢②に多少の解釈の揺れがあったとしても、明確に誤っている③を正解とすることで問題は成立しています。
このような事情から、当ブログではあえて本問を「改題」とはせず、そのまま掲載しています。