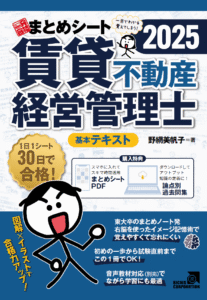今日は、平成29年度 第15問について解説します。
賃貸借契約の保証に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 保証人は、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務については、別途、保証契約を更新しない限り、保証債務を負わない。
② 連帯保証人は、貸主から保証債務の履行を求められたときに、まず借主に催告すべき旨を請求することができない。
③ 貸主が賃貸物件を第三者に譲渡した場合、保証契約は当然に終了し、保証人は新貸主との間で保証債務を負わない。
④ 賃料債務の保証人の場合は、書面または電磁的記録を作成しなくても効力が生じる。
解説
保証に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
保証人は、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務については、別途、保証契約を更新しない限り、保証債務を負わない。
×不適切です
賃貸借契約が更新された場合、保証契約自体が更新されるわけではありませんが、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、保証人は更新後の債務についても保証を継続するものとされています。
つまり、保証人は、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務については、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、保証債務を負うことになります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ②
連帯保証人は、貸主から保証債務の履行を求められたときに、まず借主に催告すべき旨を請求することができない。
〇適切です。
たとえば借主が賃料を滞納し、貸主が保証人に支払いを請求してきた場合に、保証人が「まずは借主に請求してください」と主張できる権利のことを「催告の抗弁権」といいます。
連帯保証人には、この催告の抗弁権がないため、選択肢の説明のとおり、連帯保証人は、貸主から保証債務の履行を求められたときに、まず借主に催告すべき旨を請求することができませんので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
貸主が賃貸物件を第三者に譲渡した場合、保証契約は当然に終了し、保証人は新貸主との間で保証債務を負わない。
×不適切です
保証には、債権者が変わった場合に、保証債務も新たな債権者に移転するという性質(随伴性)があります。
そのため、債権を取得した新たな債権者は、債務者が賃料を支払わないなどの債務不履行があったときには、保証人に対して保証債務の履行を請求することができます。
つまり、貸主が賃貸物件を第三者に譲渡した場合、保証契約は終了せず、保証人は新貸主との間で保証債務を負うことになります。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
賃料債務の保証人の場合は、書面または電磁的記録を作成しなくても効力が生じる。
×不適切です
保証契約は、貸主(債権者)と保証人との間で締結する契約であり、書面または電磁的記録によることが必要です。
つまり、賃料債務の保証人の場合は、書面または電磁的記録を作成しなければ効力は生じません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢②となります。
※法改正に伴い、選択肢④を改題しております。(「電磁的記録」の表現を加えるなどの一部改題を行っております。)
ぜひ関連解説もあわせて理解を深めていただければと思います。
★関連解説★