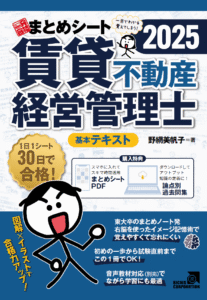今日は、平成30年度 第36問について解説します。
相続税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 所有地に賃貸住宅や賃貸ビルを建設すると、相続税の評価額の計算上、その土地は、貸家建付地となり、更地のときと比べて相続税の評価額が下がる。
② 生前贈与について相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、贈与者(親)の死亡による相続時に、この制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算をして相続税の計算を行う。
③ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数の場合は人数按分)となる。
④ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、被相続人の貸付事業用宅地等については、240㎡までの部分について80%減額することができる。
解説
相続税に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
所有地に賃貸住宅や賃貸ビルを建設すると、相続税の評価額の計算上、その土地は、貸家建付地となり、更地のときと比べて相続税の評価額が下がる。
〇適切です。
アパートなどの建物が建っている土地は貸家建付地として評価されます。
この場合、所有者が自由に使用できないため、自用地(更地)よりも評価額が低くなります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
生前贈与について相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、贈与者(親)の死亡による相続時に、この制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算をして相続税の計算を行う。
〇適切です。
相続時精算課税制度とは、基礎控除後の額が2,500万円までは贈与税がかからず、超えた部分については一律20%の贈与税が課税されるという制度です。
この制度を利用した場合、生前贈与した財産は相続発生時に相続財産に加算され、最終的に相続税の対象として精算される仕組みです。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数の場合は人数按分)となる。
〇適切です。
被相続人に、直系卑属(子など)も直系尊属(親など)もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となり、配偶者が3/4、兄弟姉妹が全体で1/4となります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です
選択肢 ④
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、被相続人の貸付事業用宅地等については、240㎡までの部分について80%減額することができる。
×不適切です。
宅地の評価額が高額となって相続税が重くなるのを防ぐため、小規模宅地等の特例が設けられています。
アパートなどの賃貸事業に使用されていた宅地は貸付事業用宅地等に該当し、200㎡までの部分については評価額が50%減額されます。
つまり、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、被相続人の貸付事業用宅地等については、200㎡までの部分について50%減額することができます。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。