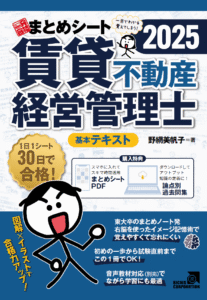今日は、令和1年度 第36問について解説します。
相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
① 法定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となる。
② 賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律30%である。
③ 賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から200㎡までの部分について50%減額することができる。
④ 相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。
解説
相続税および贈与税に関する問題です。
それではさっそく選択肢を確認しましょう。
選択肢 ①
法定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となる。
〇適切です。
相続税を算出するうえでの基礎控除額は、3,000万円に600万円を法定相続人の数だけ乗じた金額を加算して計算されます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
選択肢の場合、配偶者と子供2人の合計3人が法定相続人の数なので、選択肢の説明の通り「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となりますので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律30%である。
〇適切です。
選択肢の説明の通り、借家権割合は全国一律で30%とされていますので、この選択肢は適切です。
なお、貸家建付地の評価額を算出する計算式には、借家権割合のほかに借地権割合も用いますが、借地権割合については地域により異なります。
選択肢 ③
賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から200㎡までの部分について50%減額することができる。
〇適切です。
アパートなどの賃貸事業に使用されていた宅地は貸付事業用宅地等に該当し、200㎡までの部分については評価額が50%減額されます。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ④
相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。
×不適切です
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者(贈与を受けた人)は贈与者(贈与をした人)ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
相続時精算課税制度とは、贈与時には税金がかからないものの、生前贈与した財産は相続発生時に遺産に加算され、最終的に相続税の対象として精算される仕組みです。
基礎控除後の額が2,500万円までは贈与税がかからず、超えた部分については一律20%の贈与税が課税されます。
いったんこの制度を選択すると、その後は原則として、暦年課税制度を利用することはできなくなります。
つまり、相続時精算課税制度を選択した場合には、原則として暦年課税へ変更することはできません。よってこの選択肢は不適切です。
以上から、正解は選択肢④となります。
2025年度版 一発合格まとめシート 予約販売は5/23スタート!