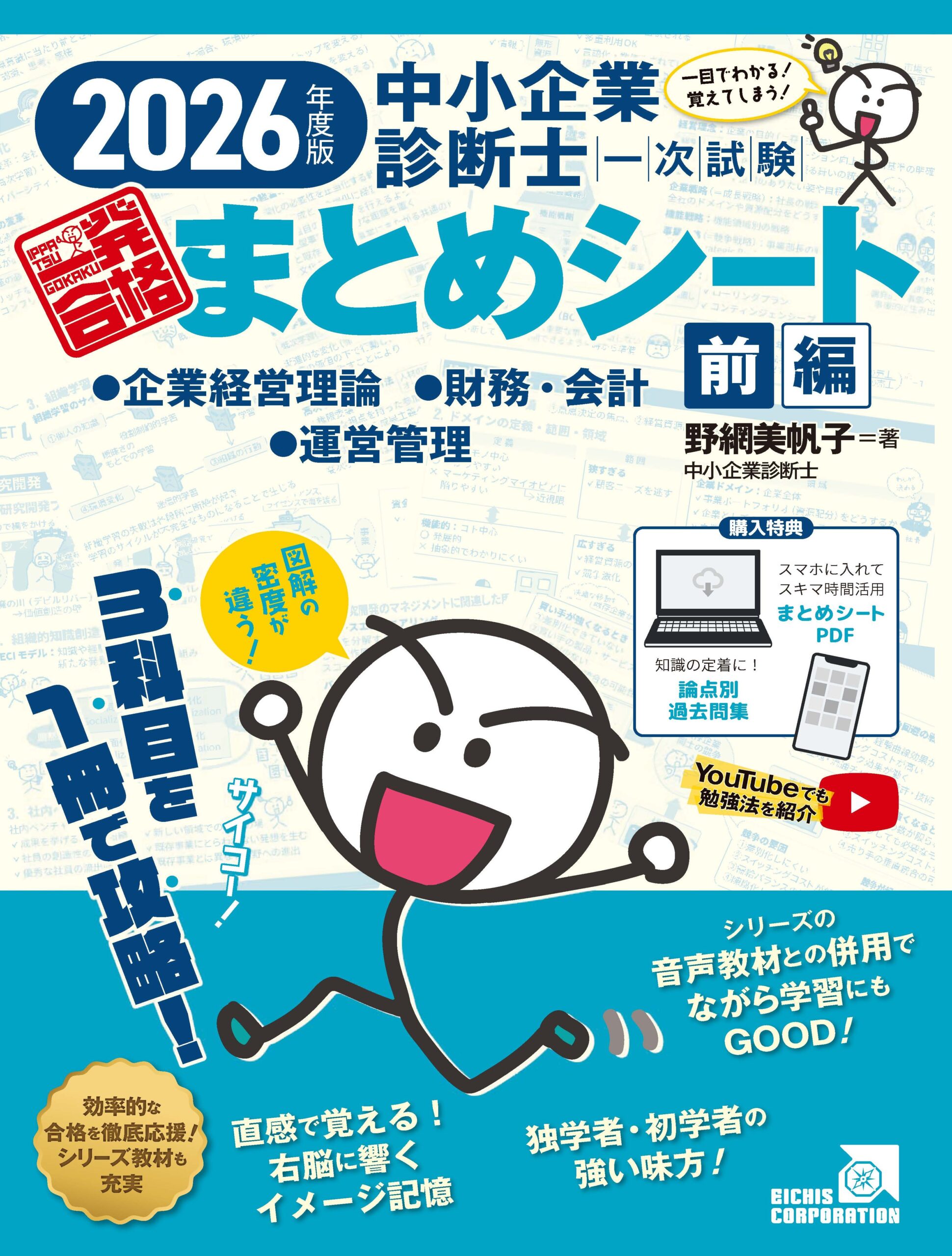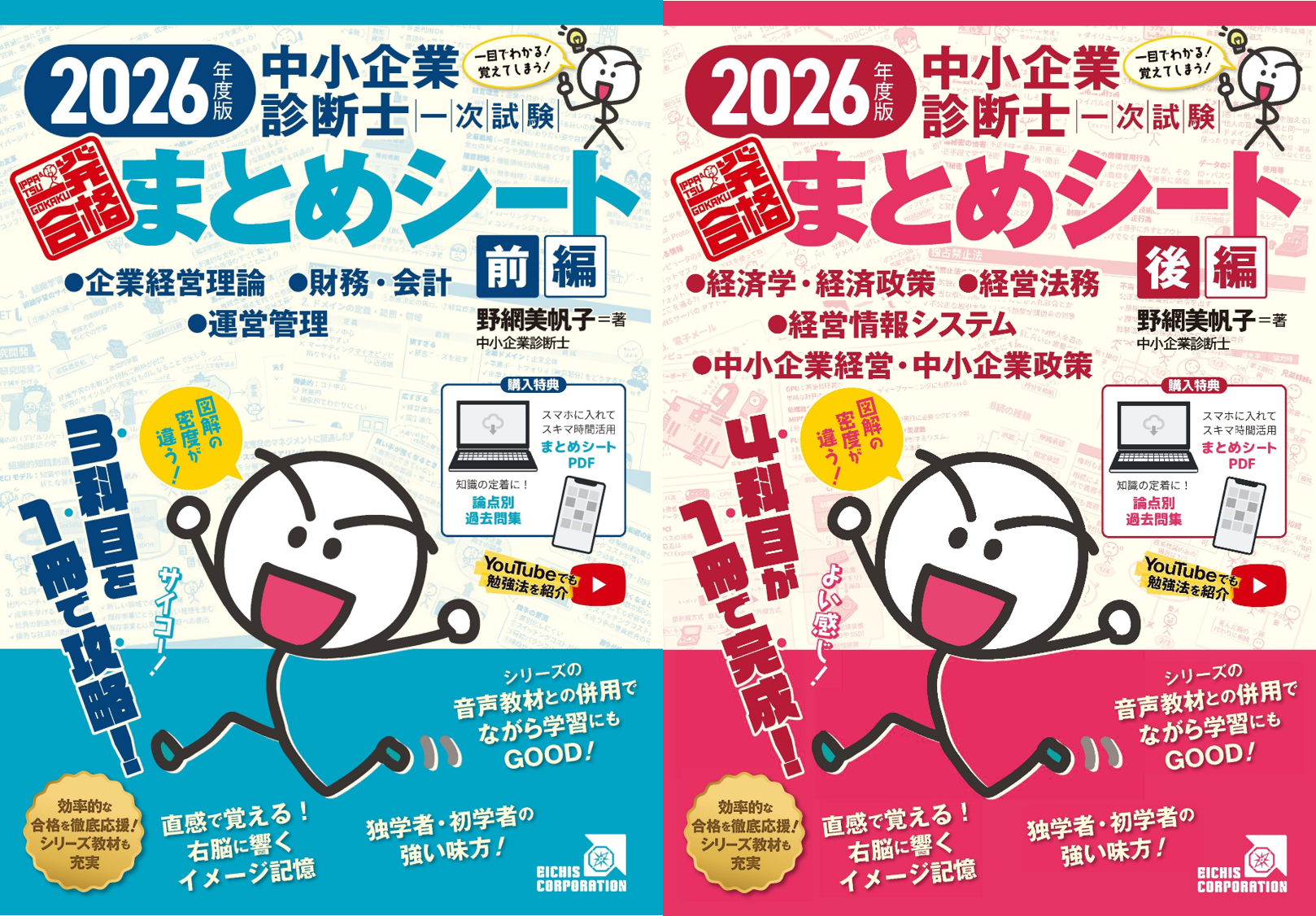今日は、企業経営理論 R3年 第35問(設問2)について解説します。
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
現代社会には、さまざまな広告①が存在する。企業は、現代の消費者に有効な広告戦略を立案するために、広告が消費者の心理や行動に及ぼす影響②を理解する必要がある。
(設問 2 )
文中の下線部②に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 飲酒運転禁止を説得テーマとして、恐怖感情とユーモア感情とを生起させる2 つの広告を作成した場合、テーマに対して高関与な消費者はユーモア感情の広告に接する方が、テーマに対して低関与な消費者は恐怖感情の広告に接する方が、それぞれ即時的に説得に賛成する態度を示す。
イ 企業からの説得意図を強く感じる広告に対して、メッセージの唱導方向と同一方向の態度を有している消費者は、その態度をさらに強化する傾向がある一方、製品への態度が曖昧な消費者は、説得意図を強く感じる内容に対して心理的リアクタンスが生じ、逆方向の態度変化を起こしやすい。
ウ 高価な製品を購入してしまい後ろめたさを感じる場合、消費者は当該ブランドの広告ばかり見たり、他ブランドの広告は見ないようにしたりして、自分の選択を正当化することが多い。「自分へのご褒美」という広告主によるメッセージは、こうした消費者が自己の購買を正当化し、認知的不協和を軽減する効果がある。
エ 製品のポジティブ要因とネガティブ要因の両方を提示することによって、製品の信憑(しんぴょう)
性を高めようとする両面提示広告では、消費者にとって低関与の製品の場合には最初にポジティブ情報を提示し、高関与の製品の場合には最後にポジティブ情報を提示した方が、それぞれ製品評価を高めることができる。
オ テレビ広告は、消費者が意識的に接触している感覚は低くても、自分にとって関心が低いブランドの広告に関しては、単純接触の回数が増えるほど、ブランドへの態度が直線的にネガティブになっていく。
解説
広告に関する問題です。
まとめシートでは、以下の通り解説しています。

「恐怖訴求」と「ユーモア訴求」は、消費者の関与度によって効果が変わります。
一般に、関与が高い人(=テーマに真剣な人)は、内容をしっかり考えるため、ユーモアのような軽い感情刺激よりも、恐怖訴求など考えさせるメッセージの方が効果的です。
一方、関与が低い人は、深く考えずに印象で判断しやすいため、ユーモアのような気軽に受け取れる刺激の方が効きやすくなります。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
広告に強い説得意図を感じると、消費者は押しつけられていると感じて反発することがあります。これを心理的リアクタンスといいます。
ただし、リアクタンスが起きやすいのは、自分の考えと広告の主張が正反対のときです。
「製品への態度が曖昧な消費者は、説得意図を強く感じる内容に対して心理的リアクタンスが生じる」という点が誤りです。
よって、この選択肢は×です。
→ ✅ 正しいです。
高価な買い物をしたあとに「ちょっと高かったかな」と不安になるのは、認知的不協和の状態です。
人はこの不快な気持ちをなくすために、「やっぱり良い買い物をした」と思いたくなります。
そのため、買ったブランドの広告ばかり見たり、他社の広告を避けたりして、自分の選択を正当化しようとします。
このとき「自分へのご褒美」といったメッセージは、「いい買い物だった」と思わせる効果があり、不協和をやわらげてくれます。
よって、この選択肢は〇です。
→ ❌ 誤りです。
両面提示広告とは、商品の良い点だけでなく、悪い点も一緒に伝えることで、信頼感を高める手法です。
ただし、「高関与なら最後にポジティブ」「低関与なら最初にポジティブ」と一概には言えません。
メッセージの長さや媒体、消費者の知識量などによって効果的な順序は変わります。
「関与度だけで順序が決まる」と言い切っている点が誤りです。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
単純接触効果(mere exposure)とは、何度も見聞きするうちに好感が高まる現象のことです。
テレビCMのように、意識していなくても繰り返し接することで、ブランドに親しみを感じるようになります。
基本的には繰り返し接触=好意が上がるのが一般的であるため「回数が増えるほどネガティブになる」という点が誤りです。
よって、この選択肢は×です。
◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
2026年度版 一発合格まとめシート
前編ご予約好評受付中!
シリーズ教材で学習効率がさらにアップ!