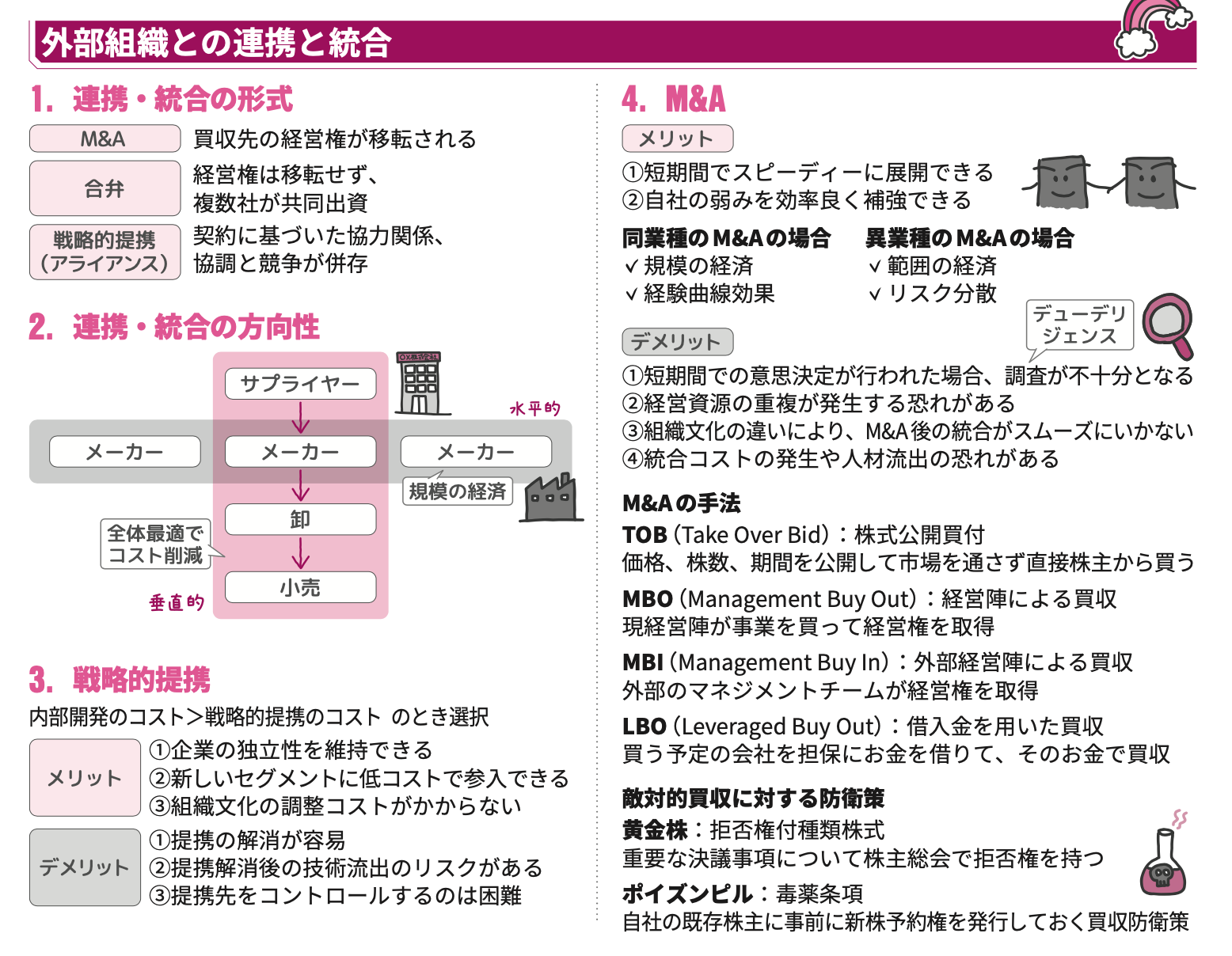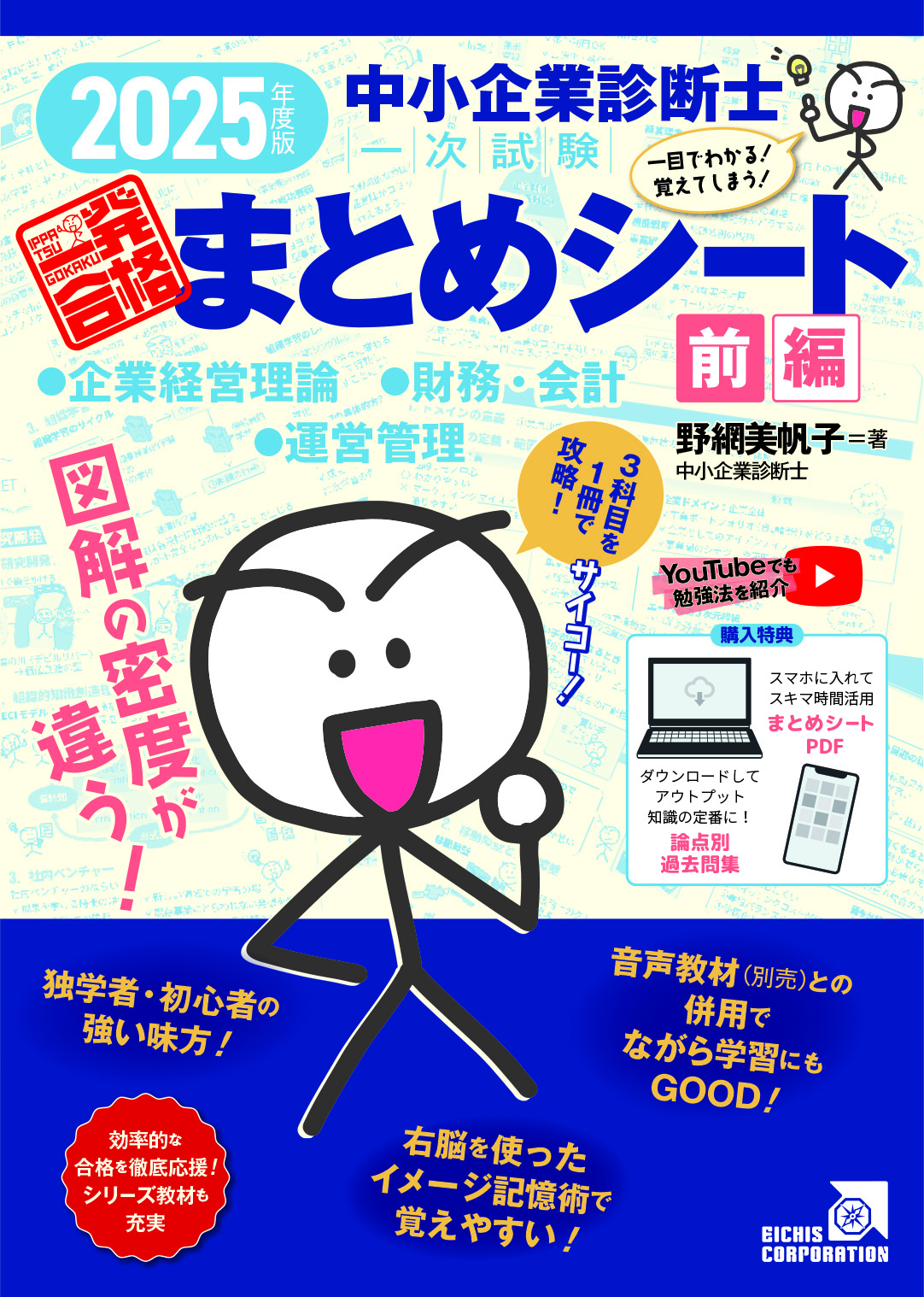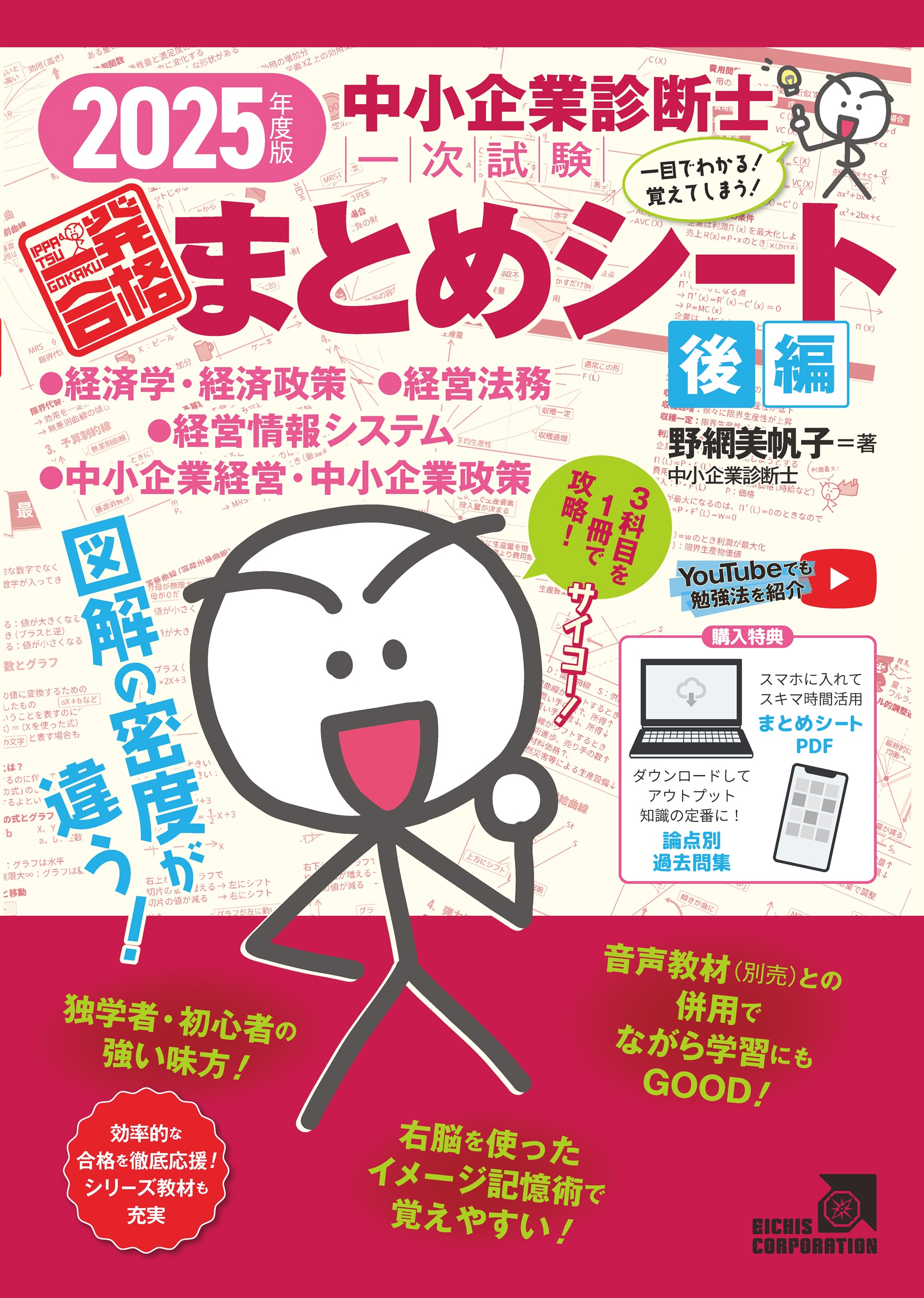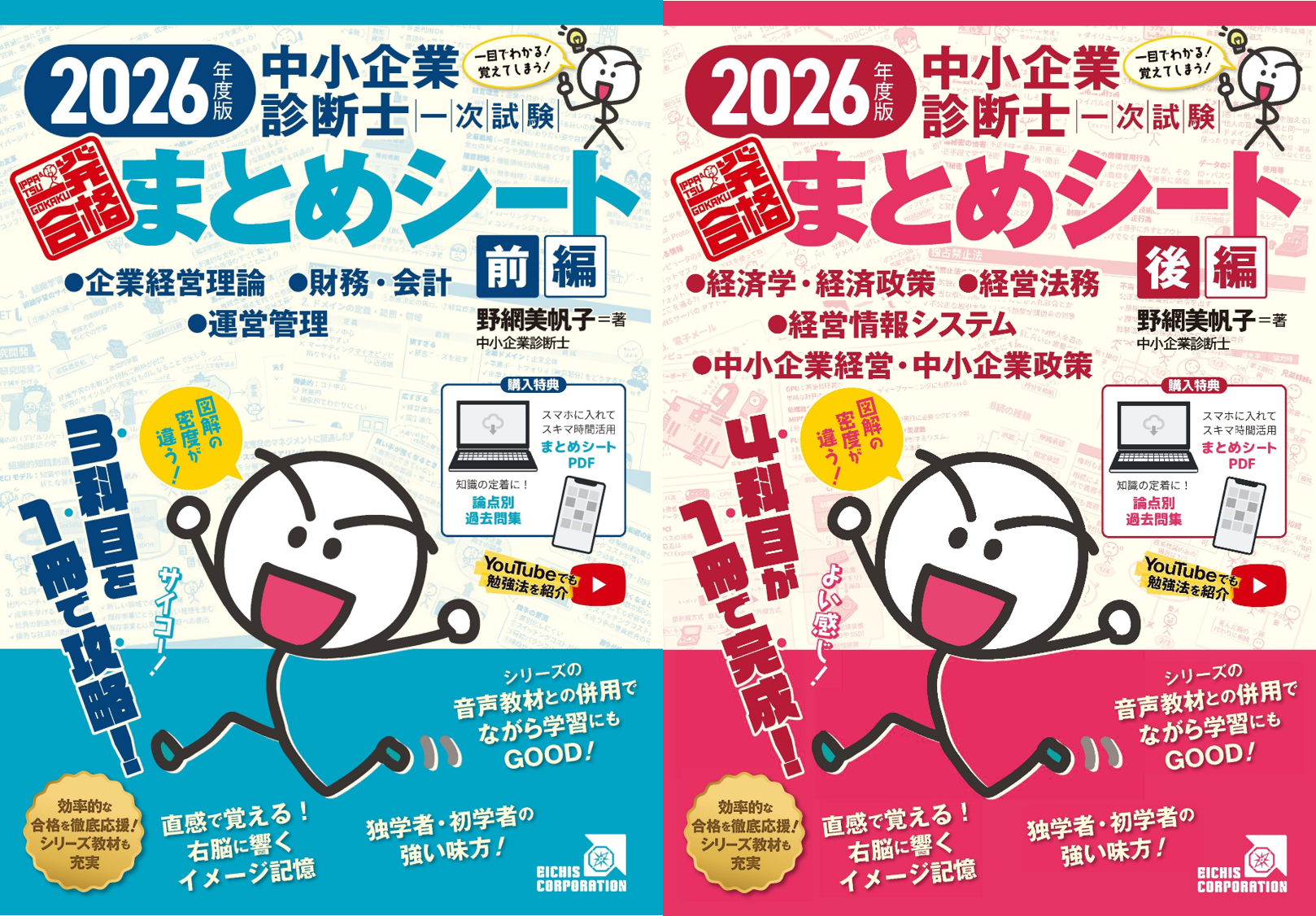今日は、R7 企業経営理論 第5問について解説します。
R7 企業経営理論 第5問
垂直統合と市場取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 市場取引から垂直統合に転換すると、市場取引の時よりも暗黙知や文脈依存的な知識は活用されにくくなる。
イ 市場取引は垂直統合に比べて調整の効率性が高く、機会主義的行動の発生を抑制できる。
ウ 垂直統合された組織では、市場取引の時に比べて、コストを削減したり機能や品質を向上させたりするインセンティブは高まる。
エ 特定の取引相手しか供給できない財を調達する場合、市場取引よりも垂直統合が選択される傾向がある。
オ 取引する財が標準化されている場合、市場取引よりも垂直統合が選択される傾向がある。
選択肢ア:市場取引から垂直統合に転換すると、市場取引の時よりも暗黙知や文脈依存的な知識は活用されにくくなる。
→ ❌ 誤りです。
→ ❌ 誤りです。
-
暗黙知(口で説明しにくいノウハウ)等は、垂直統合(自分の会社の中で働く人同士)の方が共有しやすいです。市場取引だと契約書や仕様書で説明できることしか伝わりにくいので、逆に活用しづらくなります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:市場取引は垂直統合に比べて調整の効率性が高く、機会主義的行動の発生を抑制できる。
→❌ 誤りです。
→❌ 誤りです。
- 市場取引は「価格でやりとり」できるので一見効率的ですが、資産特殊性が高い取引では機会主義的行動のリスクがあります。例えば、相手が唯一の取引先だと足元を見られる(値上げされるなど)危険等があります。これを機会主義的行動と呼びます。垂直統合の方がこういう危険は少なくなります。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:垂直統合された組織では、市場取引の時に比べて、コストを削減したり機能や品質を向上させたりするインセンティブは高まる。
→ ❌ 誤りです。
→ ❌ 誤りです。
- 垂直統合だと社内でやるので安心感はありますが、競争がない分「もっと安く・良くしよう」というプレッシャーが弱くなります。市場取引だとライバルとの競争があるため、このやる気が強まりやすいです。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:特定の取引相手しか供給できない財を調達する場合、市場取引よりも垂直統合が選択される傾向がある。
→ ✅ 正しいです。
→ ✅ 正しいです。
- 他に作れる人がいないと、その相手に依存しすぎてしまいます。自分の会社に取り込んでしまえば、ずっと供給をコントロールできます。これは取引コスト理論の基本的な考え方です。
よって、この選択肢は〇です。
選択肢オ:取引する財が標準化されている場合、市場取引よりも垂直統合が選択される傾向がある。
→ ❌ 誤りです。
→ ❌ 誤りです。
- 標準化された物は誰でも作れるので、わざわざ自分で作らず、安いところから買った方が効率的です。
よって、この選択肢は×です。
✅ 以上から、正解は選択肢エとなります。
◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
![]()
関連教材で学習効率アップ!