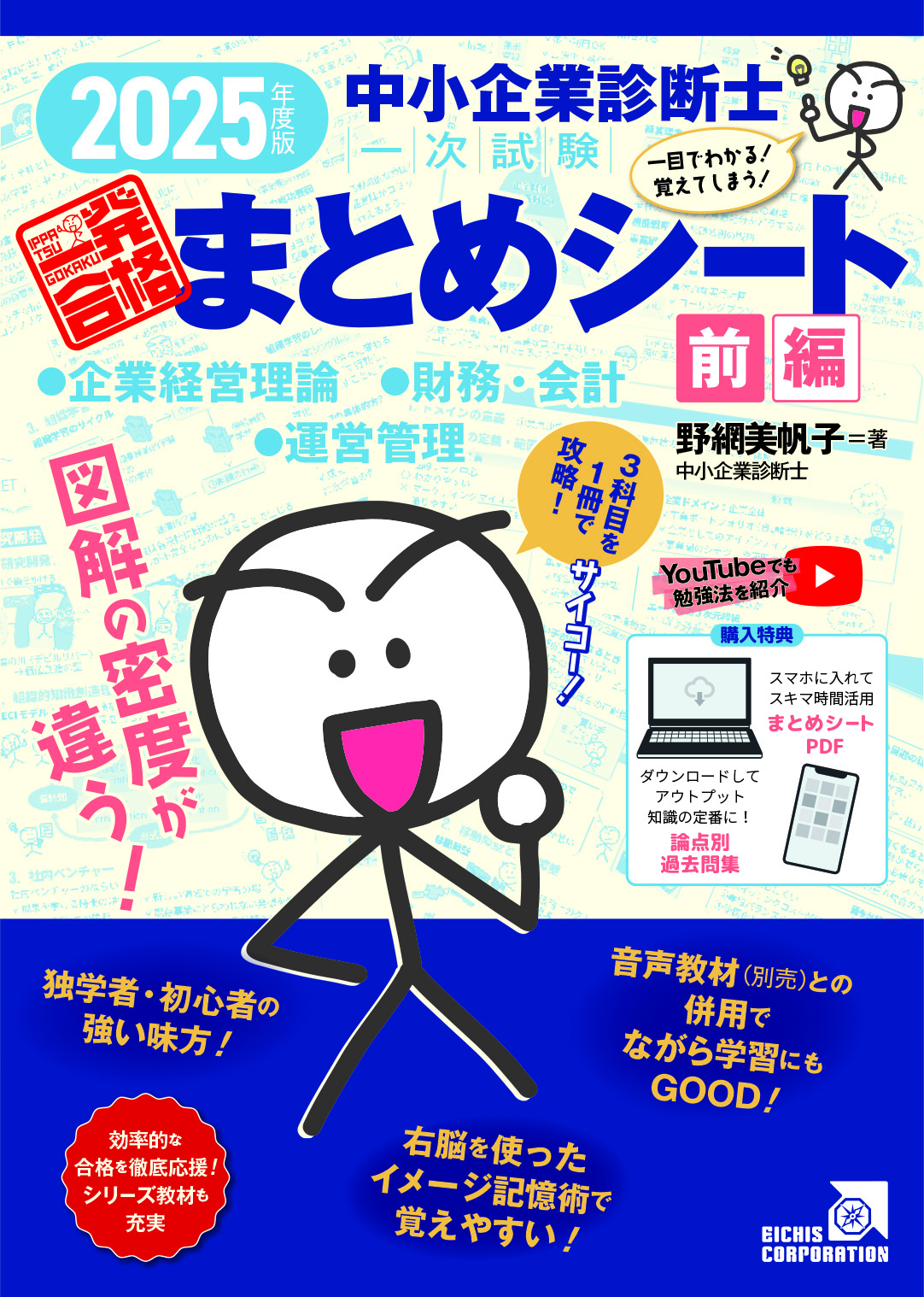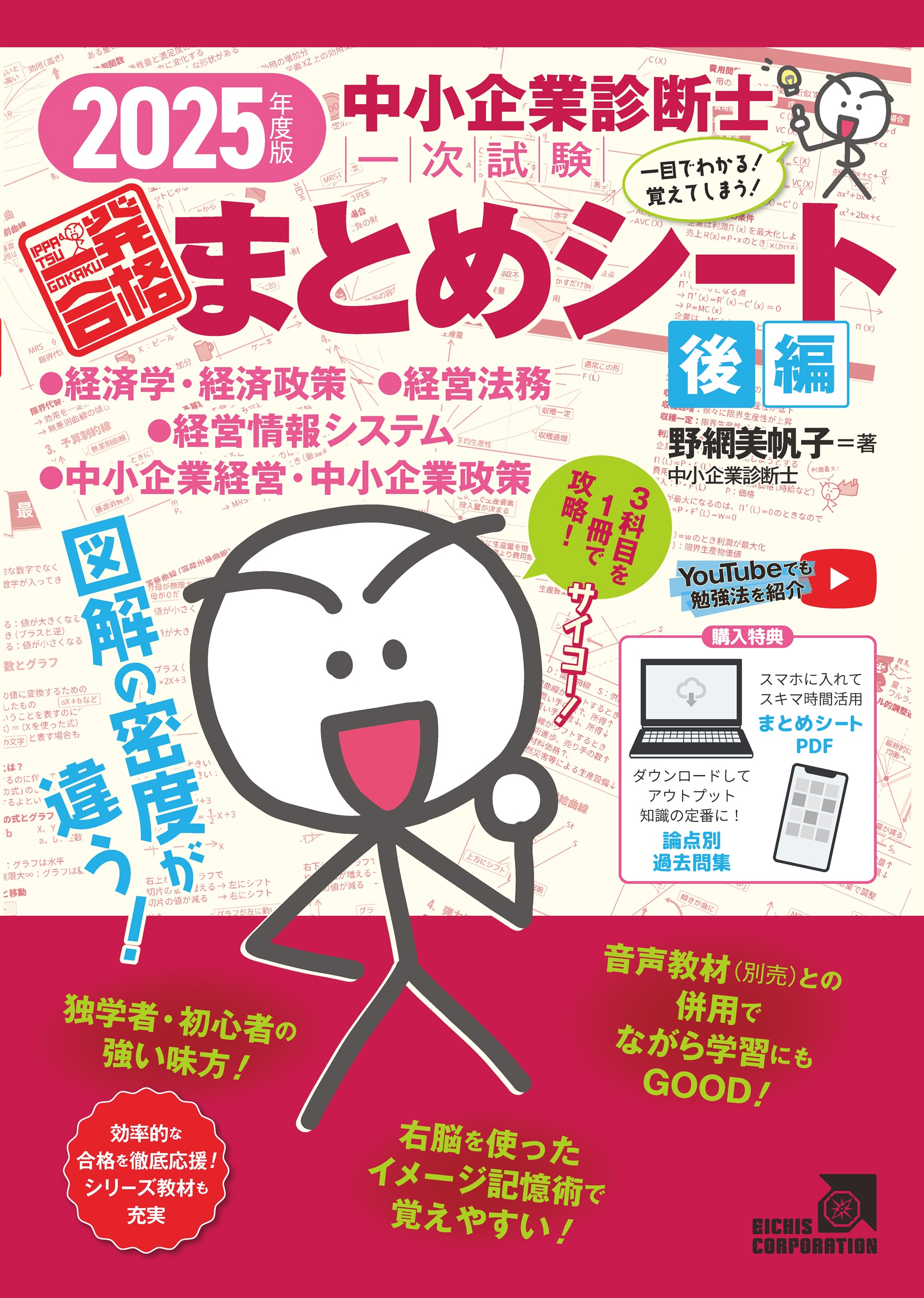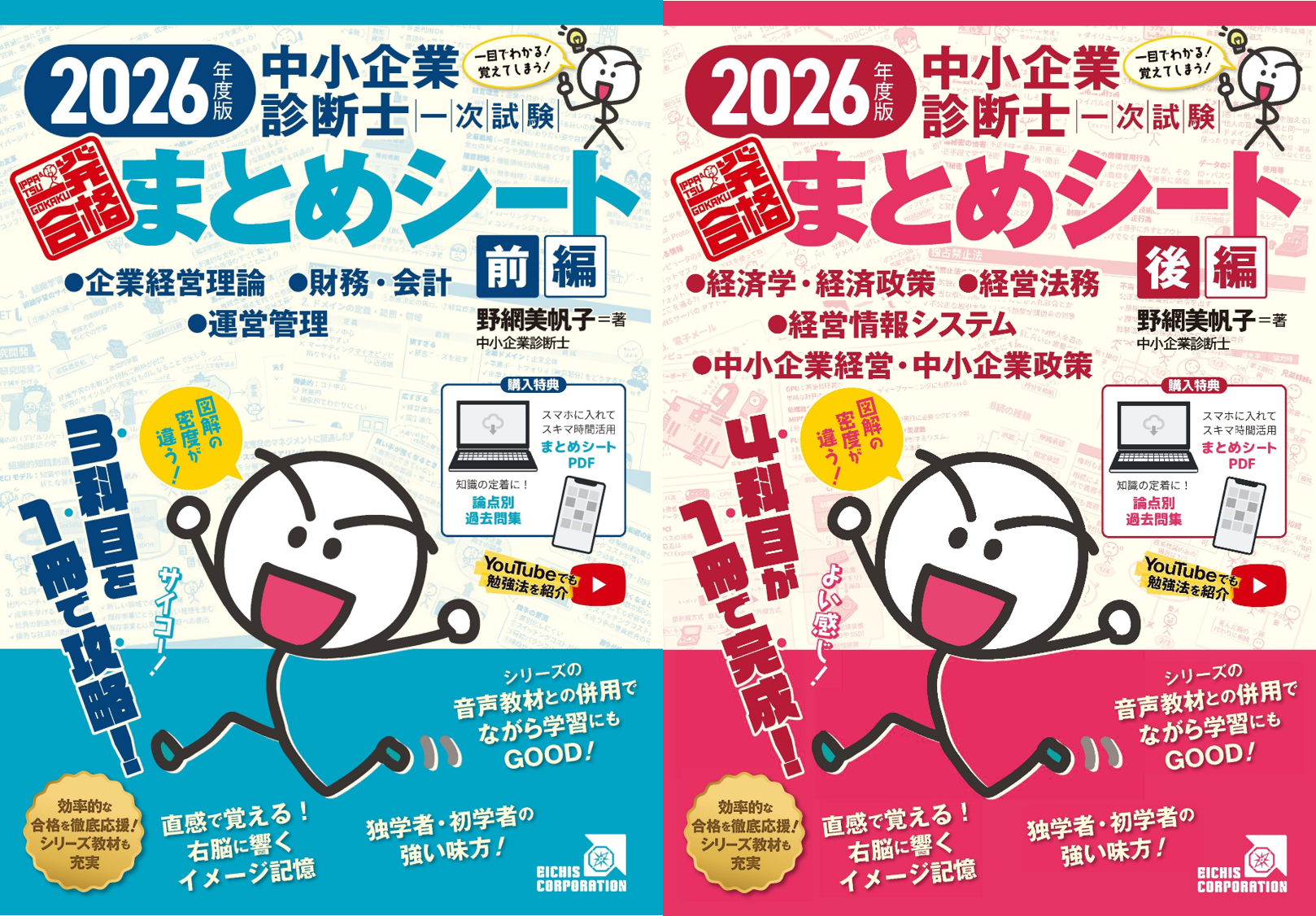今日は、R7 経営法務 第18問について解説します。
R7 経営法務 第18問
保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア 3,000万円の主たる債務について3 人の連帯保証人がいる場合、各連帯保証人はそれぞれ1,000万円の限度で連帯保証債務を負う。
イ 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、主たる債務者の配偶者であって、主たる債務者が行う事業に現に従事していない者が保証人になろうとする場合には、保証債務を履行する意思が公正証書で表示されていなくとも、その効力を生じる。
ウ 主たる債務者が破産し、免責許可決定が確定した場合、保証人はその責任を免れる。
エ 主たる債務について違約金の定めがない場合であっても、債権者と保証人の間で保証債務についてのみ、違約金の定めをすることができる。
解説
民法の保証契約についての問題です。
それでは選択肢をみていきましょう。
選択肢ア:
→ ❌ 誤りです。
複数の保証人がいる場合、各自が頭割りで計算した金額だけを負担すればよいという権利を「分別の利益」といいます。しかし、連帯保証人にはこの「分別の利益」がありません。したがって、3人の連帯保証人は、それぞれが3,000万円全額について責任を負います。債権者は、どの連帯保証人に対しても3,000万円の支払いを請求できます。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
複数の保証人がいる場合、各自が頭割りで計算した金額だけを負担すればよいという権利を「分別の利益」といいます。しかし、連帯保証人にはこの「分別の利益」がありません。したがって、3人の連帯保証人は、それぞれが3,000万円全額について責任を負います。債権者は、どの連帯保証人に対しても3,000万円の支払いを請求できます。
よって、この選択肢は×です。
選択肢イ:
→ ❌ 誤りです。
事業のために負担した貸金債務の保証契約において、主たる債務者が行う事業に現に従事していない配偶者などが保証人になる場合、保証債務を履行する意思を公正証書で表示しなければ、保証契約は効力を生じません。この規定は、保証人となる者の保護を目的としています。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
事業のために負担した貸金債務の保証契約において、主たる債務者が行う事業に現に従事していない配偶者などが保証人になる場合、保証債務を履行する意思を公正証書で表示しなければ、保証契約は効力を生じません。この規定は、保証人となる者の保護を目的としています。
よって、この選択肢は×です。
選択肢ウ:
→ ❌ 誤りです。
保証債務には、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという付従性があります。しかし、主たる債務者が破産手続で免責されても、それは債務の支払責任が免除されるだけで、債務そのものが消滅するわけではありません。破産法でも、主たる債務者の免責は保証人の責任に影響を及ぼさないと定められています。保証制度は、まさにこのような主たる債務者が支払えなくなった場合のために存在するからです。
よって、この選択肢は×です。
→ ❌ 誤りです。
保証債務には、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅するという付従性があります。しかし、主たる債務者が破産手続で免責されても、それは債務の支払責任が免除されるだけで、債務そのものが消滅するわけではありません。破産法でも、主たる債務者の免責は保証人の責任に影響を及ぼさないと定められています。保証制度は、まさにこのような主たる債務者が支払えなくなった場合のために存在するからです。
よって、この選択肢は×です。
選択肢エ:
→ ✅ 正しいです。
保証債務は、主たる債務とは別の独立した債務です。したがって、主たる債務に違約金の定めがなくても、債権者と保証人の合意により、保証債務についてのみ違約金を定めることは可能です。この違約金は、保証人が保証債務を履行しない場合に支払うべき金額として機能します。
よって、この選択肢は〇です。
→ ✅ 正しいです。
保証債務は、主たる債務とは別の独立した債務です。したがって、主たる債務に違約金の定めがなくても、債権者と保証人の合意により、保証債務についてのみ違約金を定めることは可能です。この違約金は、保証人が保証債務を履行しない場合に支払うべき金額として機能します。
よって、この選択肢は〇です。
✅ 以上から、正解は選択肢エとなります。
◆ブログ村参加しています◆
気に入っていただけたら、クリックお願いします!
![]()
関連教材で学習効率アップ!